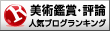パリジェンヌは戦い 世田谷美術館 パリジェンヌ展 3/24
世田谷美術館のパリジェンヌ展に行ってきた。
面白かった。めっちゃメモ取ってたら、監視員の人が書類ばさみ貸してくれた。やさしい。
ゲアダ・ヴィーイナ「スコットランドシルクのベスト、ねずみ色の綿の厚手クレープのスカート『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』より、プレート170」1914年

全体的にタイトルが長い。
売店にこの猫のぬいぐるみが大量に売っててめっちゃブサ可愛くて買うか迷った…うちのリアル猫に壊されるから買わなかったけど。
この展示をどう捉えるべきなのだろうかと図録を読みながら考えていたら、なんだか時間がかかって展示が終わってしまった。ので、素直に思ったことを書こうと思う。
なので今回はあまり美術の話はしない。
唐突なんだけど、私は差別というものが正直よく理解できていない。
あるのだということも解るし、おそらくは無自覚なだけで自分でもしてしまっているのだろうと思うけれど、たまに直面すると「え?なんでそんな発想になるの??」という驚きが先に立ってしまう。
それは多分私が良い教育を受けているとか躾がちゃんとされているからではなく、単に狭い世界で生きてきたからなのだろうと思う。同種の人間しかいないところでは差別は明確に起こりづらい。単一民族しかいないところで人種差別は起こらないし、女性しかいないところで性差別は起こらないという単純なことだったのだろうと思う。
要は無知なのだ。
最近ちょっとやべーなと思い始めていたりする。
ジャン=オノレ・フラゴナール「良き母親」1777-79年頃

まるまると太った子供、安全で美しい庭、若くやさしく美しい母。
伝統的な理想的母子像と言えるかもしれない。けれども。
これは決して“伝統的"などではないとこの展示では解説される。
そもそも、「子供を母親が育てる」ということが上流階級ではありえないことであった。貴族や王族の子供たちは生まれると早々に親から引き離され、乳母に育てられるのが慣例だった。これはヨーロッパに限った話ではなく、日本だってそうだ。
というか、そもそも「無垢でか弱く庇護対象である子供」という概念自体が、18世紀に生まれたものだ。
当時女性はすでに、ファッショナブルな美しさ、小粋な会話でサロンを主催する知性、室内調度を流行に即して整えるセンス、使用人を監督して家庭を管理する能力を求められていた。それらに加えて「穏やかで完璧な母性」をも求められるようになったという事実が紹介されている。
あれ、これ、普通の美術展じゃなくね?
---------------
トマ・クチュール「未亡人」1840年

喪服に身を包んだはかなげな美女。
夫を失った彼女は、この後どのような人生を送るのだろうか?
この時代、特に上流階級の女性に置いて、まともな仕事などは存在しない。女性が一人で街を歩くこともまともにできなかった時代だ。彼女が自分や子供を養える仕事に就くことはまず無理だろう。
誰かと再婚をするのが一般的な身の振り方なのだろうと思う。
その彼女の悲しみを、こうして娯楽として消耗することに戸惑いを覚える。
また、不幸にして身を持ち崩してしまった、働き口が無く娼婦となった女性に対する世間の目は恐ろしく厳しい。
これミュシャ展の時も思ったのだけれど、娼婦に異様に厳しくない?"ふしだら"な女性が一人いるとして、周りには"ふしだら"な男性が複数いるはずなのだけれど、なぜ女性ばかり責められるの?なぜ女性が男性を堕落させたことになるの?男性が彼女たちを利用しなければいいんじゃないか、もっと社会福祉をすればよいのではないか、そもそも限られた狭い役割以外を許さないのをやめて仕事を普通にやらせればいいのではないかと思う。
---------------
ポール・ガヴァルニ(イポリット・ギョーム・シュウルピス・シュヴァリエ)
E.ド・B.(ボーモン)婦人「ラルティスト」<女性芸術家たち>より 1856年

家庭の中で良き妻良き母である限りは、世間は女性に優しい。
(前略)だが、心配には及ばない。彼女は聴衆のために演奏しようとしているのではない。彼女は普段着の姿だ。自分自身のためだけに弾くのである。(後略)
「女性芸術家たち」というタイトルがつけられたシリーズでは、芸術家たる女性が、家庭内で趣味としてのみ活動していることが強調されている。
そもそも、芸術家として認められるために必須だったアカデミーへの入会が、女性は認められていない。
---------------
オノレ・ドーミエ<青鞜派>第7図「母親は創作に熱中し、子供は浴槽の中」1844年

家庭の範囲を超えて芸術家を目指そうとする女性に対しての目はぎょっとするほどだ。
いま「青鞜派」といえば女性芸術家として自立した強く現代的な女性たち、という印象だろう。平塚らいてうのこともあって、政治的というイメージもあるかもしれない。
けれど当時の社会の目がこれだ。自分のことに没頭して家庭を顧みず、子供すら不注意で殺してしまう。
こんなことが実際にあったとは思えない。思えないけれど、ねつ造して嘲笑してよい存在ではあったようだ。
---------------
オノレ・ドーミエ 「半社交界(ドゥミ・モンド)の女性が半スカートを着ているわけではない」

ドゥミ・モンドというのは昔ながらの貴族ではなく、新興の成金達、特に女性に関して言うならば娼婦達のことだ。
18世紀から20世紀、女性の服の流行は常に厳しい目が向けられている。派手な格好、奇抜な髪型の貴族女性の絵画を見たことがないだろうか。ただのファッションプレートだけでなく、こうした風刺画で極端に戯画化されたものも多い。
この絵ではスカートのボリュームがあまりにも大きくなったことを風刺している。
しかしこのタイトルからもわかるように「社交界にいるべきでない人間が社交界の服装をしていること」を皮肉っているように、このボリューミーなスカートは社会規範として女性に求められているものなのだ。
一方でドレスコードを強制し、一方でそれを揶揄する。その神経ってなんなんだろう。
18世紀に流行した高く結い上げる髪型や、19世紀のシュミーズドレスをモスリン病と、バカにする資格が誰にあるんだろうか。そしてこの風刺画が今でも伝わり、ファッションを優先にした愚かな人達という印象操作を受けているのはなんなんだろう。
こういうのは本当は、男性の、男性による、男性のための内輪ネタなんだろうなと思う。シャルリー・エブドの国だなぁ。変わんなぁなぁと思うけど。
日本だって1990年代の女子高生をヤマンバってバカにしてたよなぁとか考えちゃう。
---------------
フランソワ・グザヴィエ・サジェ「パリの街を行く」製作年不詳

パリジェンヌ展、と言いながら、女性がパリの街を歩く姿は少ない。だいたいの絵は室内の写真だし、屋外にいる場合は複数人で連れ立った様子が描かれている。
19世紀後半になってやっと増えだした女性芸術家の描く絵は、静物画が多い。
もちろん、好き好んでではない。一人で自由に外を歩くことができないのだ。
女性が一人でいれば、男性からの声が必ずかかるそうした様子がこのポストカードにも表されている。
---------------
左:ジョセフ・ルロランタン・レオン・ボナ「メアリー・シアーズ」1878年
右:レギーナ・レラング「カルダン」1958年

パリジェンヌ展のキャッチコピー「憧れるのは、なぜ。」
なぜかと問われれば、彼女たちが強いからだろうと思う。時代に押し込められ、不自由を押しつけられ、反抗すれば嘲笑される。それでも自分であるために抗い、しっかりと立ち続ける。その強さがパリジェンヌを作っているのだろうと思う。
「今日のパリジェンヌは、つんとした鼻をもち、その赤い唇は官能性をあらわにする一方で、長いまつげの下の目は無関心さを意味している」
そう表現されたパリジェンヌの姿は、100年の時を経ても変わらないものなのだ。